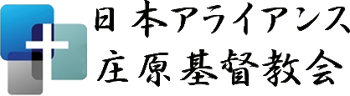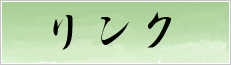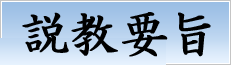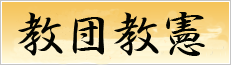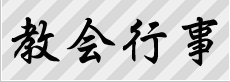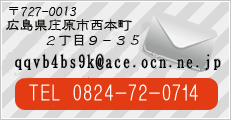説教要旨
◇2026年2月22日 ガラテヤ4:1-7 「あなた方は子である」 先週の水曜日から受難節に入りました。「いわゆるこの世のもろもろの霊力の下に、縛られていた」、罪の奴隷となっていた私たちを御子のあがないによって救い出してくださいました。コロサイ1章にこうある通りです。「神は、わたしたちをやみの力から救い出して、その愛する御子の支配下に移して下さった。」 イエス様もヨハネ8章にあるようにこう語られました。 「もしわたしの言葉のうちにとどまっておるなら、あなたがたは、ほんとうにわたしの弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理は、あなたがたに自由を得させるであろう」。 この「自由」という言葉に律法学者たちは反発しました。 「わたしたちはアブラハムの子孫であって、人の奴隷になったことなどは、一度もない。どうして、あなたがたに自由を得させるであろうと、言われるのか」、そしてイエス様は語られました。 「よくよくあなたがたに言っておく。すべて罪を犯す者は罪の奴隷である。そして、奴隷はいつまでも家にいる者ではない。しかし、子はいつまでもいる。だから、もし子があなたがたに自由を得させるならば、あなたがたは、ほんとうに自由な者となるのである。」 イエス様はゲッセマネの園で苦しみながら「アバ、父よ」と祈られました。そしてその贖いのおかげで私たちも子とされ、父なる神を「アバ、父よ」と呼ぶことが出来るのです。
◇2026年2月15日 ガラテヤ3:15-29 「キリストに連れて行く養育掛」 「わたしたちは生れながらのユダヤ人であって、異邦人なる罪人ではない」と語られたように、神の民イスラエル・ユダヤ人の誇りは絶大でした。しかしパウロは、神様は「アブラハムに、『あなたによって、すべての国民は祝福されるであろう』との良い知らせを、予告した」と語ります。 イエス様はサマリヤの女性に言われました。「女よ、わたしの言うことを信じなさい。あなたがたが、この山でも、またエルサレムでもない所で、父を礼拝する時が来る。あなたがたは自分の知らないものを拝んでいるが、わたしたちは知っているかたを礼拝している。救はユダヤ人から来るからである。しかし、まことの礼拝をする者たちが、霊とまこととをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今きている。父は、このような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も、霊とまこととをもって礼拝すべきである」。 ヨナ書に「ましてわたしは十二万あまりの、右左をわきまえない人々と、あまたの家畜とのいるこの大きな町ニネベを、惜しまないでいられようか」とあるように、ユダヤ人だけが救いに関してすべてであると語っておられるのではありません。すべての人は罪人であり、律法を成し遂げることが出来ず、ただ主の十字架のあがないによって義とされ、感謝をもってイエス様の御名により神様に呼ばわるのです。
◇2026年2月8日 ガラテヤ3:1-14 「祝福が異邦人に及ぶため」 パウロに神様は人間の歩みのいかに誤りの多いかを示されました。ユダヤ人たちはこう信じていました。「わたしたちは生れながらのユダヤ人であって、異邦人なる罪人ではない」(ガラテヤ2:15) それが神に選ばれた民、律法の民。神に選びだされ、神様の栄光を現わす民。しかし旧約聖書に描かれている通り、イスラエルは、ユダヤ人は神に選ばれた民ではありながら、世界の模範としての民ではありませんでした。「義人はいない、一人もいない」と書かれている通りです。 「人の義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただキリスト・イエスを信じる信仰による」、これがイエス様が与えてくださった新しい契約です。古い契約を無効にされたのではなく、律法を守ることによって義とされるに人は本当に力ない存在であるが故の唯一の救済措置でした。 しかし人は律法を守ることによって義とされる道をあきらめず、自分は大丈夫だと高をくくっています。そして時の祭司長も律法学者たちもイエス様を十字架につけるという大罪を犯しました。 救いはユダヤ人のためのものではなくて、全世界の民のものであるということは当の昔にアブラハムに語られていたことなのに、それなのにユダヤ人たちは特権階級でいたがりました。彼らは異邦人を罪びと呼ばわりしましたが、自分たちもまたそうであることに目をつぶっていたのです。主の恵みに目を留めましょう。
◇2026年2月1日 ガラテヤ2:11-21 「わたしのためにご自身をささげられた神の御子」 「わたしが現に走っており、またすでに走ってきたことが、むだにならないため」、「わたしたちは、福音の真理があなたがたのもとに常にとどまっているように、瞬時も彼らの強要に屈服しなかった」。 パウロは福音の真理を巡って戦っていました。もはや二度と人をとりこにする「むなしいだましごとの哲学」(コロサイ2:8)に捉えられることがないように、「人間から受けたのでも教えられたのでもなく、ただイエス・キリストの啓示によっ」て進み続けました。彼は「わたしが切実な思いで待ち望むことは…大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも、わたしの身によってキリストがあがめられること…わたしにとっては、生きることはキリストであり、死ぬことは益」(ピリピ1:20-21)と言い、天で安息を得るまでは命がけで、死に物狂いでただキリストによって生き、キリストを現すことを願っていました。 「福音の真理に従ってまっすぐに歩」くということにおいて彼は妥協せず、彼は大先輩であるペテロに対しても、全く恐れることなく面と向かって反対し、抵抗しました。それは福音の真理に従って進み、とどまり続けることが生命線だとつくづく知っていたからです。「人の義とされるのは律法の行いによるのではなく、…わたしを愛し、わたしのためにご自身をささげられた神の御子を信じる信仰による」キリストの贖いの死による「神の恵み」に感謝します。
◇2026年1月25日 ガラテヤ2:1-10 「おもだった人たち」 あのダマスコ途上の劇的な回心から後、パウロが使徒としての活動をするに至って、ガラテヤ書によれば長い時が過ぎていたことが分かります。使徒行伝ではすっと書かれていることですが、パウロが何を重んじていたのかが分かり、興味深いです。 「異邦人の間に宣べ伝えさせるために、御子をわたしの内に啓示して下さった時、わたしは直ちに、血肉に相談もせず、また先輩の使徒たちに会うためにエルサレムにも上らず、アラビヤに出て行った。それから再びダマスコに帰った。その後三年たってから、わたしはケパをたずねてエルサレムに上り、彼のもとに十五日間、滞在した」…「その後十四年たってから、わたしはバルナバと一緒に、テトスをも連れて、再びエルサレムに上った。 そこに上ったのは、啓示によってである。そして、わたしが異邦人の間に宣べ伝えている福音を、人々に示し、「重だった人たち」には個人的に示した。それは、わたしが現に走っており、またすでに走ってきたことが、むだにならないためである。」 「もう一つの福音」と語り、福音とは相容れないものがまことしやかにもう一つの福音としてはびこっている、それは異邦人に対して割礼を強いることであったことが分かります。それはユダヤ教からキリスト教への成長に向かって大切なことでした。パウロは教えの確かさ、福音の真理に立ち、二度と人による誤りによって教えが揺るがされないようにと努めたのです
◇2026年1月18日 ガラテヤ1:11-24 「人間によるものではない」 「わたしが宣べ伝えた福音は人間によるものではない。わたしは、それを人間から受けたのでも教えられたのでもなく、ただイエス・キリストの啓示によったのである」。前回の所にもこうありました。「人々からでもなく、人によってでもなく、イエス・キリストと彼を死人の中からよみがえらせた父なる神とによって立てられた使徒パウロ」。彼はどうしてかくも何度も同じことを強調するのでしょうか。 彼は熱心に教えに奉じるにあたって二度と過ちを犯したくなかったのです。これが真実だと信じていった先に、それが全くの嘘であり過ちであったという絶望を二度と味わいたくなかったのです。 本当にそれは信じられるのか。間違いないのか。人生を、命を懸けて従っていけるのか。今度は大丈夫なのか。彼はそれを徹底的に確かめようとしました。人に取り入ることもせず、距離を置いて観察し、そこに神様の働きがあるのか、人の意図でも人の努力でもなく、人のつながりによってのみ維持されているのでもなく、そこには確かに神様のお働きがあるのかどうか…。彼は徹底的にそれを見つめ、隠遁の後にペテロに会いました。彼もまた「神のことを思わず人のことを思っている」と主から叱責され、また3度までも主を否む失敗をしながらも主の恵みのうちに「岩」と呼ばれる者でした。かつての迫害者が帰られたことを主に讃美する群れの美しい姿にも目が留まります。
◇2026年1月11日 ガラテヤ1:1-10 「キリストの僕」 今年の聖句を「キリスト・イエスにあっては、割礼があってもなくても、問題ではない。尊いのは、愛によって働く信仰だけである」に定め、ガラテヤ書から読み進めようとしております。 キリスト教とは何であって何ではないのか、書簡の冒頭からくっきりと描かれています。 「人々からでもなく、人によってでもなく、イエス・キリストと彼を死人の中からよみがえらせた父なる神とによって立てられた使徒パウロ」。ここに彼の出発点が明確に示されています。 パウロはかつて高名なガマリエルの弟子として名をはせ、キリスト教の迫害に奔走していました。 しかし主イエスキリストを迫害することに向かわせたその学びは間違いであったということ、そのことは彼にとっての大きな衝撃でした。もう二度と間違いのわだちを踏みたくない。彼は徹底的に事の本質を知り極めようとしました。 人が作り出した教えではなくて、人づてに手垢がついた人間本位に変質した教えではなくて、神様ご自身から手渡された源泉を手に入れたい。彼はその戦いを始めたのです。このことは私たちにとっても重要な意味を持ちます。キリスト教的なことを知るのではなく、キリストそのものを知るのです。何がキリストの教えであって何がそうではないのかをもう一度徹底的に調べ上げるのです。私たちはこの年の初めにまずそのことから始めようではありませんか。
◇2026年1月4日 詩篇1篇・ヨハネ3:16-21 「神にあってなされたことが明らかに」 詩篇1篇とヨハネ3章。いずれも悪しき者と正しい者の対比が描かれています。 詩篇において正しい者とは、神様の助言、忠告、目的を幸せと喜び、祝福と考える人たちであり、悪しき人の道に立たず、とどまらず、あざけり、傲慢に語る人たちのところに座らず、とどまり住むことはありません。なぜならば彼らにとっては主の教え、導きと指南とが喜びであり、心の恋い慕う願望だからです。彼は神様の教えを夜に昼に思い、口ずさみます。原語では「うめく」という語が使われます。 御言葉を思い、口ずさむということ、これは常に喜ばしく軽やかな口ずさみばかりではなくて、時にはうめきでもあるということ、それはどういうことでしょうか。 悪しき人の道に立たず、とどまらず、座り込んでとどまり、住むことはない。この表現は、その道にどっぷりと留まる事を指します。主を信頼する者にも、意図せずとも危険を横切ったり、その地に踏み入ってしまう危険があることを示唆しています。うめきもあります。混沌も迷いもあります。しかしうめきながらでも私たちは御言葉を口ずさみます。迷いの所、失敗の場所、疑いの地。そこにも救いが残されている。それが私たちの喜びです。一方悪しき人たちは迷いもなく流されて行きます。その道は滅びです。しかし神様はイエス様を通して滅びの道からの救いを与えてくださったのです。いつも光に向けて進みましょう。
◇2025年12月28日 ルカ2:22-40 「今あなたの救いを見た」 一年の最後の礼拝の時を迎えております。様々なことがありましたが、すべて神様に支えられ、導かれて今があることを感謝いたします。 最悪の状況、受け入れがたい、信じられない、信じたくない現実があるでしょうか。しかしザカリヤもエリサベツも、マリヤもヨセフも、後になってみれば神様のおっしゃったことは必ずなる、祈りは聞かれる、神様は万事を最善に導かれるという事を悟りました。 「すべての訓練は、当座は、喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛えられる者に、平安な義の実を結ばせるようになる。」(へブル12:11) 新しい年も神様への信頼と信仰により私たちは生かしていただけるのです。私たちには生きる道があります。 「エルサレムにシメオンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼に宿っていた。そして主のつかわす救主に会うまでは死ぬことはないと、聖霊の示しを受けていた。」 私たちには慰めと救いが必要です。この傷付き疲れ果てた世界は主の慰めを受けなければ立ち行かないところにあります。皆が愛と慰めに飢え渇いています。救いを求めています。私たちもこの世界に主の救いが現れるのを、多くの方々の慰めと救いのリバイバルをこの目で見るまでは死ねないと熱く祈るとき、主が結果を見せて下さるでしょう。
◇2025年12月21日 ルカ2:1-21 「すべての民に与えられる大きな喜び」 「全世界の人口調査をせよとの勅令」。ローマ皇帝の権力は絶大でした。「全世界の」人々が一人の王の命令一下で動き出すのです。4500万人とも数えられる帝国ローマを動かす者は世界を動かす。皇帝はそういう権力をもって世界に対して勅令を出しました。 ヨセフとマリヤもその動きの中に翻弄される人たちでした。ナザレからベツレヘム、それは150kmにも及ぶ旅で標高差もあり、徒歩では1週間もかかる道のりです。マリヤはすでに身重になっており、行きの道のりは大丈夫でしたが、「ところが」実家ナザレに帰る前、ヨセフの本籍地、ダビデの町ベツレヘムにいる間に産気づいてしまいました。 しかし私たちは全ての舞台が整ったということが分かるのです。イエス様は「主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼はとこしえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう」との御使いの言葉の通りにダビデの町で生まれるのです。ダビデの町ベツレヘム(パンの家という意味)。それはイスラエルが飢饉のときモアブに逃れた後夫も息子も失ったナオミがルツと共に戻った町、ルツはボアズと出会い、ダビデの祖父オベデが生まれたのです。 神様は全世界を牛耳る帝国の皇帝をも手のひらに載せ、ご自分の御業をなさいます。神様のわざは全て時にかなって美しい。私たちも恐れを喜びに変えてくださる神様のすべての御業を信じて讃美する人生が与えられているのです。
◇2025年12月14日 ルカ1:57-80 「われらの足を平和の道へ導く」 アドベントも第3週。いよいよ来週はクリスマス礼拝です。 ザカリヤは自分の知恵や考えに固執するあまり、神様の尊いご計画を受け入れることが出来ず、大衆の面前で神様の裁きを受けて物言えぬ人となりました。 「ぐうの音も出ない」とはこのことでしょう。彼は起こるはずもないと勝手に決めつけていた妻エリサベツの懐胎を、その膨らみ続けるおなかを見るにつれ、文字通り何も言えずにただ見守っていました。 「人の心には多くの計画がある、しかしただ主の、み旨だけが堅く立つ」(箴言19:21) 主の御旨に従いわが子をヨハネと命名した時、彼に癒しが訪れました。彼は讃美して言いました。 「主なるイスラエルの神は、ほむべきかな。神はその民を顧みてこれをあがない、わたしたちのために救の角を僕ダビデの家にお立てになった…わたしたちを敵から、またすべてわたしたちを憎む者の手から、救い出すため…わたしたちを敵の手から救い出し、 生きている限り、きよく正しく、みまえに恐れなく仕えさせてくださるため」「これはわたしたちの神のあわれみ深いみこころによる。また、そのあわれみによって、日の光が上からわたしたちに臨み、 暗黒と死の陰とに住む者を照し、わたしたちの足を平和の道へ導く」 「わたしに悪しき道のあるかないかを見て、わたしをとこしえの道に導いてください。」主の憐れみによる回復の道に感謝いたします。
2025年12月7日 ルカ1:46-56 「そのあわれみは代々限りなく」 アドベントの2本目のろうそくが立ちました。再来週はクリスマス礼拝、アドベントの聖書も、主のご降誕に向け、ストーリーは進んでいきます。 「どうして、そんな事があり得ましょうか。わたしにはまだ夫がありませんのに」。素晴らしい神様の出来事の実現に一役買いたいけれども自分にはその能力がない。不可能だ。どう考えても現状ではお役に立てない。そういうマリヤの応答でした。しかし御使いの答えは「聖霊があなたに臨み、いと高き者の力があなたをおおうでしょう。それゆえに、生れ出る子は聖なるものであり、神の子と、となえられるでしょう…あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています…神には、なんでもできないことはありません」とのものでした。取り急ぎエリサベツの元へと向かうマリヤ。「主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、なんとさいわいなことでしょう」との慰め深い言葉を聞き、マリヤの喜びは爆発します。 「わたしの魂は主をあがめ、 わたしの霊は救主なる神をたたえます。この卑しい女をさえ、心にかけてくださいました。今からのち代々の人々は、わたしをさいわいな女と言うでしょう、力あるかたが、わたしに大きな事をしてくださったからです。そのあわれみは、代々限りなく主をかしこみ恐れる者に及びます。」 主は弱く心許ない私たちを見出し、任命し、強め、用い、大いなることを成し私たちを喜びに満たしてくださいます。
◇2025年11月30日 ルカ1:8-45 「いと高き者の力があなたをおおう」 アドベント(待降節)に入りました。暗き世に光を照らすため、救いと命を与えるために生まれた主に感謝します。 エリサベツとマリヤの懐胎と、御使いによる予告の記事ですが、好対照の特徴を持つ人の応答が描かれています。 「ザカリヤよ、あなたの祈が聞きいれられた」、祈りも何十年も経ってから聞かれると、祈ったことも忘れてしまいますが、神様は最善のタイミングで答えてくださいます。「時が来れば成就するわたしの言葉」です。「彼はあなたに喜びと楽しみとをもたらし、多くの人々もその誕生を喜ぶ」そのような子が生まれ、母エリサベツは、マリアの挨拶の声を聞いてこの子がおなかの中で動き、「子供が胎内で喜びおどりました。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、なんとさいわいなことでしょう」と語りました。 クリスマスは喜びです。タイミングや方法は人の予期するところではありませんでしたが、「神には、なんでもできないことはありません」。畏れることはないのです。「聖霊があなたに臨み、いと高き者の力があなたをおおうでしょう。それゆえに、生れ出る子は聖なるものであり、神の子」という奇跡は起こるのです。 「見よ」という言葉、人の注意を促す言葉が5回出てくるのも注目です。神様は私たちに語り掛け、力を持って臨み、事を成就してくださいます。私たちも信じて目を見張り、受け入れて恵みを得るのです。
◇2025年11月23日 コロサイ4:2-18 「神の国のために働く同労者」 冒頭には、パウロの切実な祈りの勧めと要請があります。 「目をさまして、感謝のうちに祈り、ひたすら祈り続けなさい。同時にわたしたちのためにも、神が御言のために門を開いて下さって、わたしたちがキリストの奥義を語れるように…また、わたしが語るべきことをはっきりと語れるように、祈ってほしい。」 パウロの祈り求めはどこに向いていたのでしょうか。それは2回繰り返して語られているように「語れるように」ということでした。「神が御言のために門を開いて下さって、わたしたちがキリストの奥義を語れるように」これは獄の門が開かれて外に出て人々に語れるようにという意味と、御言葉を語ることが出来るように天の門を開いて知恵と啓示とを与えてくださいという意味があると思います。 「語るべきことをはっきりと語れるように」。また、「今の時を生かして用い、そとの人に対して賢く行動しなさい。 いつも、塩で味つけられた、やさしい言葉を使いなさい。そうすれば、ひとりびとりに対してどう答えるべきか、わかるであろう」との御言葉は、いかに語り行動するのかを求め生きる指針となります。 「あなたがたが全き人となり、神の御旨をことごとく確信して立つように」、「この三人だけが神の国のために働く同労者であって、わたしの慰めとなった者」、「人々のために、ひじょうに心労している」これらの主の僕から多くの学びをいただきます。
2025年11月16日 コロサイ3:17-4:1 「あなたがたは、主キリストに仕えている」 「あなたのすることはすべて、言葉によるとわざによるとを問わず、いっさい主イエスの名によってなし、彼によって父なる神に感謝しなさい」。信仰の実践について簡潔に言い表す一言だと思います。 「キリストの名において」。 「私は父の名代(みょうだい)としてまいりました」という時には、その人の代理として、代わりを務めるという意味ですが、「いっさい主イエスの名によって」なすということは、そういうことを言っているのではないでしょうか。 今日の箇所では、妻へ、夫へ、子供へ、僕へ、僕の主人へ、具体的な命令が書かれています。「仕えなさい・従いなさい」、それが、主にある者にふさわしいこと、主に喜ばれることであると書かれ、「何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から働きなさい」と、17節の「いっさい主イエスの名によってなし…」との言葉が繰り返されます。 主に対するように従うということは、夫や父や、主人もまたそれに見合う者であるべきで、それは神様が私たちを愛してくださるように愛し、いらだたせたり、失望したりしないように励ますことであり、気分次第の横暴ではなくて正しく公平に扱うことであり、それらはすべて神様がまず私たちにお示しくださったことなのです。「何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から働」く。それは人を見ずして神様を見て、神様に感謝をお返しして仕え従うことなのです。
◇2025年11月9日 コロサイ3:14-17 「彼によって父なる神に感謝しなさい」 「キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい」、「キリストの言葉を、あなたがたのうちに豊かに宿らせなさい」、そして「あなたのすることはすべて、言葉によるとわざによるとを問わず、いっさい主イエスの名によってなし…」、「いつも感謝していなさい」、「感謝して心から神をほめたたえなさい」、「彼(キリスト)によって父なる神に感謝しなさい」という風に、今日の箇所には3度「イエスキリストによって」「感謝しなさい」との教えが描かれています。 「キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい」とは、直訳すれば、「キリストの平和と調和を裁判官・審査員・アンパイヤ(審判)としてあなた方の心の中に迎えて行動しなさい」となります。いつも心の中に信号を持っていて、これは青信号、黄信号、赤信号と、キリストにある平和と調和が私たちに語り掛けるのです。キリストは常に父なる神様との深い調和を愛して、愛と謙遜という平和に根差して歩んでいらしたことを深く思い、私たちの行動の原理とします。そのようにして、「キリストの言葉を、あなたがたのうちに豊かに宿らせ」、「言葉によるとわざによるとを問わず、いっさい主イエスの名によってなし」ていくのです。それが互いに教え訓戒し合う内容であり、そこから父なる神様への感謝と賛美が広がっていくのです。ここには数限りない感謝への道があるのです。
◇2025年11月2日 1コリント13:1-13 「最も大いなるもの」 庄原にランバス宣教師が来られてから140年。それから10年を経て、宣教師のもとに洗礼を受けた教会員が誕生し、教会が成長し、吉舎、油木、東城など県北へと拡大していきました。私たちは今、庄原教会の130周年を祝うとともに、いつまでも変わらないものに、しかと目を向けたいと思います。いつまでも存続するもの、それは愛です。 「預言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また、山を移すほどの強い信仰」があったら私たちの人生も教会の未来も安泰であると言えるでしょうか。しかし、「預言はすたれ、異言はやみ、知識はすたれる」のです。「わたしたちの知るところは一部分であり、預言するところも一部分にすぎない」のです。 「今は、鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。…その時には、顔と顔とを合わせて、見る…。わたしの知るところは、今は一部分にすぎない。…その時には、わたしが完全に知られているように、完全に知るであろう。」 わたしが御使いの言葉を話したとしても、わたしに預言する力があったとしても、わたしに強い信仰や、犠牲的な行動があったとしても、それらは不完全です。古い時代のくぐもった鏡で顔を見るようなものです。子供の時代に幼稚に考えていたことを捨て去った大人のように、私たちは完全なものを知ることが出来るのです。それが神の愛です。愛してくださる神様に目を留めるのです。
◇2025年10月26日 コロサイ3:11-14 「愛はすべてを完全に結ぶ帯」 先週の箇所の最後のところにはこうありました。 「造り主のかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのである。」 真の知識とは何でしょうか。 「キリストがすべてであり、すべてのもののうちにいますのである。…あわれみの心、慈愛、謙そん、柔和、寛容を身に着けなさい。互に忍びあい、もし互に責むべきことがあれば、ゆるし合いなさい。主もあなたがたをゆるして下さったのだから…あなたがたもゆるし合いなさい。これらいっさいのものの上に、愛を加えなさい。愛は、すべてを完全に結ぶ帯である。」 これが真の知識、完全なる知識であり律法です。 「律法の全体は、「自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ」というこの一句に尽きる」(ガラテヤ5:14) 「そこには、もはやギリシヤ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開の人、スクテヤ人、奴隷、自由人の差別はない。キリストがすべてであり…」との記述は興味深いです。ユダヤ人はギリシャ人を異邦人と言い、自分たちは割礼の民であり、無割礼の異邦人ではないと言います。しかしギリシャやローマの人たちは自分たちは未開の人や、(自分たちの宗教になぞらえて)異教徒や無神論者や異端者ではないと言います。自由人たちは自分は奴隷のような身分ではないと言います。人々は互いに違いを持ち、互いに壁を持ち、分断しています。そこを結び合わせるのがキリストにある神の愛です。赦しの愛なのです。
◇2025年10月19日 コロサイ3:4-10 「真の知識に至る新しき人を着た」 先週の箇所では、私たちは死んだ者であるという事が書いてありました。 「もしあなたがたが、キリストと共に死んで世のもろもろの霊力から離れたのなら、なぜ、なおこの世に生きているもののように…」、「あなたがたはすでに死んだものであって、あなたがたのいのちは、キリストと共に神のうちに隠されているのである。」 しかしこうも書いてあります。 「だから、地上の肢体、すなわち、不品行、汚れ、情欲、悪欲、また貪欲を殺してしまいなさい。」「しかし今は、これらいっさいのことを捨て、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を、捨ててしまいなさい。互にうそを言ってはならない。あなたがたは、古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨て、…」 すでに死んでしまったのならば古き力は台頭しないはずです。その力に引き寄せられることもないはずです。しかし、私たちはなおも肉の性質を殺し続け、捨て続け、脱ぎ捨て続けなければならないのです。 しかし私たちは当てもない永遠の修練の旅路に投げ捨てられているのではありません。孤独な戦いではありません。 「あなたがたは、古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨て、造り主のかたちに従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのである」私たちは汚れた服を脱いで新しくされ、真の知識に至る新しい人を着ています。さっぱりときれいになった私たちがどうしてまた薄汚い衣を着なおす必要があるのでしょうか。感謝です。
◇2025年10月12日 コロサイ2:20-3:3 「上にあるものを思う」 「『さわるな、味わうな、触れるな』…という人間の規定…ひとりよがりの礼拝とわざとらしい謙そんと、からだの苦行…知恵のあるしわざらしく見えるが、実は、ほしいままな肉欲を防ぐのに、なんの役にも立つものではない」 「これらは、きたるべきものの影であって、その本体はキリストにある。」 「完全な自由の律法を一心に見つめてたゆまない人は、聞いて忘れてしまう人ではなくて、実際に行う人である。こういう人は、その行いによって祝福される。もし人が信心深い者だと自任しながら、舌を制することをせず、自分の心を欺いているならば、その人の信心はむなしいものである。父なる神のみまえに清く汚れのない信心とは、困っている孤児や、やもめを見舞い、自らは世の汚れに染まずに、身を清く保つことにほかならない。」(ヤコブ書1章) 「キリスト・イエスにあっては、割礼があってもなくても、問題ではない。尊いのは、愛によって働く信仰だけである。…わたしは命じる、御霊によって歩きなさい。そうすれば、決して肉の欲を満たすことはない。…御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、 柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。キリスト・イエスに属する者は、自分の肉を、その情と欲と共に十字架につけてしまった…」(ガラテヤ5章) イエス様が私たちのためになしてくださった救い、霊によって生まれ変わる道を開いて下さったことに感謝します。
◇2025年10月5日 コロサイ2:13-19 「神に育てられて成長していく」 「あなたがたは、先には罪の中にあり、かつ肉の割礼がないままで死んでいた者である」。 前節まで、高らかに救いの素晴らしさが語られていたのに、急にまた逆戻りしたような表現です。前節はこうでした。 「あなたがたはまた、彼にあって、手によらない割礼、…キリストの割礼を受けて、肉のからだを脱ぎ捨てたのである。あなたがたはバプテスマを受けて彼と共に葬られ、同時に、彼を死人の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によって、彼と共によみがえらされたのである」 「あなたがたは、先には罪の中にあり、かつ肉の割礼がないままで死んでいた者であるが、神は、あなたがたをキリストと共に生かし、わたしたちのいっさいの罪をゆるして下さった。」 これは逆戻りではなく、大切なことの強調です。罪の中にあって、神様の前には死にもたとえられるような悲惨な状態だった。選民でもなく、異邦人だった。しかしキリストの割礼により、滅びゆく古き我に死に、キリストの贖いにより赦され、キリストと共に生きる者にして頂いたのです。 「もろもろの支配と権威との武装を解除し、キリストにあって凱旋し、彼らをその行列に加えて、さらしものとされた…キリストなるかしらに、しっかりと着く…からだ全体は、…強められ結び合わされ、神に育てられて成長していく」 私たちは救いと命のかしら、王の王である主に結び合わされているのです。
◇2025年9月28日 コロサイ2:6-12 「キリストにあって、それに満たされている」 今日の箇所には「キリストにあって」という言葉が6回出てきます。彼にあって歩きなさい(6節)、彼に根ざし、彼にあって建てられ(7節)、キリストにこそ、満ちみちているいっさいの神の徳が、かたちをとって宿っており(9節)、キリストにあって、それに満たされている(10節)、彼にあって、手によらない割礼、すなわち、キリストの割礼を受けて(11節)、バプテスマを受けて彼と共に葬られ、同時に、彼を死人の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によって、彼と共によみがえらされた(12節)。 そして、「満ちみちている」や「満たされる」とか、「支配と権威」「力」という言葉も繰り返し出てきます。 一方で、「むなしいだましごとの哲学で、人のとりこにされないように、気をつけなさい。それはキリストに従わず、世のもろもろの霊力に従う人間の言伝えに基くもの」とか、「(人間の)手によらない割礼」とか、キリストによらない、頼らない生き方についても示されています。 私たちは12節にありますように、「あなたがたはバプテスマを受けて彼と共に葬られ、同時に、彼を死人の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によって、彼と共によみがえらされた」のですから、人となられた神であるイエス様に教えられつつ生きることをひたすら求めていこうではありませんか。 (マタイ11章28-30節)
◇2025年9月21日 コロサイ2:1-6 「神の奥義なるキリスト」 「わたしが、あなたがたとラオデキヤにいる人たちのため、また、直接にはまだ会ったことのない人々のために、どんなに苦闘しているか、わかってもらいたい。」…パウロは牢の中で苦闘していました。それは何の苦闘だったのでしょうか。 「それは彼らが、心を励まされ、愛によって結び合わされ、豊かな理解力を十分に与えられ、神の奥義なるキリストを知るに至るためである。 キリストのうちには、知恵と知識との宝が、いっさい隠されている。わたしがこう言うのは、あなたがたが、だれにも巧みな言葉で迷わされることのないためである。」 会ったことのある人も、ない人も。獄の中にありて、顔と顔とを合わせることの出来ない状況にて、駆けて行って話したいという気持ちでパウロはしたためます。神の奥義なるキリストを知りなさい。 知恵と知識、識別力、隠された秘儀、宝。それらはキリストのうちに満ち満ちています。 しかし、巧みな言葉がありました。魅力的に思える言葉ですが、それは偽りなのです。 「あなたがたの秩序正しい様子とキリストに対するあなたがたの強固な信仰とを見て、喜んでいる。このように、あなたがたは主キリスト・イエスを受けいれたのだから、彼にあって歩きなさい。」 「神は無秩序の神ではなく、平和の神である。」(1コリント14:33)神様はイエス様による救いにより罪のもたらす混沌から命と秩序と平和に導いてくださいました。
◇2025年9月14日 コロサイ1:24-29 「うちにいますキリスト、栄光の望み」
「今わたしは、あなたがたのための苦難を喜んで受けており、キリストのからだなる教会のために、キリストの苦しみのなお足りないところを、わたしの肉体をもって補っている。」 獄中にあるパウロのさらなる決意が記されてあります。
この自分の体をもって、キリストの身体である教会のために、キリストの苦しみのなお足りないところを補っている、苦難を喜んでいる…。獄の中で、またさまざまの苦難の中でその意味を考え進むパウロが至った答えであろうと思います。
私たちは出来れば苦難を避けたいと思います。そのように祈りもしていると思います。しかしここにあるこの言葉に目を留めましょう。
「今わたしは、あなたがたのための苦難を喜んで受けており」…。
パウロも出来れば苦しみを避けたかったに違いありません。そしてイエス様でさえ、ゲッセマネの園にて出来ることならこの苦き杯を取り去ってくださいと祈られました。しかし、この苦しみにより目の前にいる人々が救われるのならば、自分の苦痛は喜んで受ける、それが教会の体のために自分の体を捧げるという事なのだと思います。目の前にいる人を助ける、それはどうやってもたらされるかと言えば、それが具体的には「神の言を告げひろめる務」です。
「この奥義は、あなたがたのうちにいますキリストであり、栄光の望みである。」
◇2025年9月7日 コロサイ1:15-23 「キリストは教会のかしら」
「御子は、見えない神のかたちであって、すべての造られたものに先だって生れたかたである」との御言葉がありますが、これはイエス様が初めからおられた永遠の神ではなくて、万物の創造の前のその時に生まれ、創られた最初の被造物だという意味なのでしょうか。そうではありません。これはイエス様がすべての被造物の世界が始まる前からおられた方であり、すべての被造物にまさる神であるという事を指します。
「御子は、見えない神のかたち」です。イエス様はこう語られました。
「わたしを見た者は、父を見たのである」(ヨハネ14:9)
「万物は、天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も、支配も権威も、みな御子にあって造られたからである。これらいっさいのものは、御子によって造られ、御子のために造られたのである。 彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。
そして自らは、そのからだなる教会のかしらである。彼は初めの者であり、死人の中から最初に生れたかたである。それは、ご自身がすべてのことにおいて第一の者となるためである。」このようなお方、死から復活された方が教会のかしらであり、この方がかしらとして第一の方となり、私たちが続いていくことが出来るとは、何と力強いことでしょうか。この世の中のものすべてを作られたお方が私たちと共にいてくださるのです。
◇2025年8月31日 コロサイ1:9-14 「愛する御子の支配下に」
神の恵みと愛とは、それを人々が本当に悟った時から人を愛の人へと作り変え、世界中で実を結ばせる力強いものであることを先週学びました。
その愛は、すべての聖徒たちへと分け隔てなく注がれる愛として表され、そのことは獄中のパウロの耳にも達し、パウロは「あなたがたが御霊によっていだいている愛を、わたしたちに知らせてくれた」と喜びました。
それを聞いてパウロはさらにこう祈ります。
「あなたがたがあらゆる霊的な知恵と理解力とをもって、神の御旨を深く知り、主のみこころにかなった生活をして真に主を喜ばせ、あらゆる良いわざを行って実を結び、神を知る知識をいよいよ増し加えるに至ること」
この祈りをパウロはやめないで祈り続けると語ります。
神の御心を知る知識が満たされる、あらゆる霊的な知恵と理解力。これを私達も求めて行きたいのです。私たちの
全ての願いや喜び、それらは何の上に成り立っているのでしょうか。私たち一人一人の個人的な喜びや計画、そういうものももちろんあると思いますが、それらは神様も望んでおられることです。すべての思いを一度神様に委ねて、神様の望まれ、喜ばれるという土台の上に私たちのすべての行い、行動をお任せして待ち望むときに、よい業が生まれ、良き実を実らせ、その実践を通してますます神様を知る知識が増し加えられます。
罪赦され光の子とされたのでそうすることが出来るのです。
◇2025年8月24日 コロサイ1:1-8 「福音の真理の言葉によって」
今日からコロサイ書に入ります。今日の御言葉から、次の御言葉が連想されます。
「いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。」(1コリント13:13)
「キリスト・イエスにあっては、割礼があってもなくても、問題ではない。尊いのは、愛によって働く信仰だけである。」(ガラテヤ5:6)
パウロは地中海世界にイエス・キリストの死と復活による神の救いを伝える働きに活躍しましたが、その働きの中で彼はそのよい知らせ、福音の真実さを、リアリティ、真実性をまざまざと感じました。
「この福音は、世界中いたる所でそうであるように、あなたがたのところでも、これを聞いて神の恵みを知ったとき以来、実を結んで成長しているのである。」
そしてこの聖句には大切なことが語られています。福音の真理は救いと望みを与えるのですが、私たちは福音をただ聞くだけではその力にあずかることはできません。「これを聞いて神の恵みを知ったとき以来」、「神の恵みを聞いて真に悟った日から」(新共同訳)、「神を真理であり、真実であり、頼ることの出来る現実のものとしてその恵みを知り理解した時から」実を結んで成長するのです。
このように神様の恵みを現実のものと信じる者には希望が満ち溢れ、そしてまた愛が満ち溢れるのです。実を見れば木の良し悪しが分かるのです。
(マタイ7章)
◇2025年8月17日 使徒4:32-37 「大きなめぐみが、彼ら一同に」
先週は1コリント12章から、私たちは皆一つ体であるという事を聖書から学びました。
「からだの中に分裂がなく、それぞれの肢体が互にいたわり合うため…もし一つの肢体が悩めば、ほかの肢体もみな共に悩み、一つの肢体が尊ばれると、ほかの肢体もみな共に喜ぶ。あなたがたはキリストのからだであり、ひとりびとりはその肢体である。」
キリストはこの体-つまり信じるようにと恵みによって導かれた私たちを愛し、その尊い命をもって贖い、私たちを正なる主のお体の一部分としてくださいました。頭なる主に感謝をささげ、一つ身体が支え合い、高め合い、助け合い、互いに満たすのです。このような素晴らしい共同体がほかにあるでしょうか。
「主よ、いま、…僕たちに、思い切って大胆に御言葉を語らせて下さい。そしてみ手を伸ばしていやしをなし、聖なる僕イエスの名によって、しるしと奇跡とを行わせて下さい。…使徒たちは主イエスの復活について、非常に力強くあかしをした。そして大きなめぐみが、彼ら一同に注がれた。彼らの中に乏しい者は、ひとりもいなかった。」
この御言葉に、主イエス様につながる共同体の命と躍動を感じます。
1コリント13章の有名な御言葉はこう語ります。
「いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。」
いつまでも存続する愛を受け、伝えたいと願います。
◇2025年8月10日 1コリント12:12-27 「互いにいたわり合うため」
「からだの中に分裂がなく、それぞれの肢体が互にいたわり合うため…もし一つの肢体が悩めば、ほかの肢体もみな共に悩み、一つの肢体が尊ばれると、ほかの肢体もみな共に喜ぶ あなたがたはキリストのからだであり、ひとりびとりはその肢体である」
キリストをかしらとする、全世界の歴史的で有機的な体としての集合体は、いかに大きいものなのでしょうか。
体にはおびただしい細胞があり、ありとあらゆる組織や器官があって一つの体が形成されているように、キリストにつながれて、キリストの命によって生かされている聖徒たちの作り上げる身体はどのように素晴らしいものでしょうか。そしてどのように素晴らしい励まし合いと助け合いとの中に私たちの命が育まれているかを知ります。
天に帰られ、今私たちが会うことの出来ない、信仰にある方々も、イエス様の体として今、私たちとつながっています。
皆同じ体の一部分として分裂がなく、互いにいたわり合い、愛し合い、気遣いをし合って生きていくすばらしさを教わります。誰が上でだれが下ではなくて、目立たない、小さく見える部分こそが尊ばれ、目立つ部分も慎みを持ち、調和とハーモニーがあり、苦しみも喜びも分かち合い、いたわり合う家族。一つキリストの身体があり、わたくしたちはそのキリストの身体の一部分として分かち合う切っても切れない部分として迎え入れられている喜びを思います。
◇2025年8月3日 使徒4:23-31 「大胆に御言葉を語らせて下さい」
「ただ、これ以上このことが民衆の間にひろまらないように、今後はこの名によって、いっさいだれにも語ってはいけないと、おどしてやろうではないか」-投獄と共に脅しによって、役人、長老、律法学者たち、大祭司とその一族が集まってペテロとヨハネを取り囲みましたが、彼らははっきりと宣言しました。「神に聞き従うよりも、あなたがたに聞き従う方が、神の前に正しいかどうか、判断してもらいたい。わたしたちとしては、自分の見たこと聞いたことを、語らないわけにはいかない」。
美しの門のところでのイエス様の御名による癒しは、ペテロとヨハネとを窮地に立たせる大きな出来事となりましたが、「聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろう」とのイエス様の約束に基づいた、聖霊による力によるイエス様の証しを留めることなど決してできませんでした。彼らの心はイエス様に繋がっていました。彼らの心からイエス様を取り除くこと、そしてその証をやめさせることは出来ませんでした。
全ては聖書の預言の通り、迫害も起こりますが、神様はそれよりもはるかに勝るお力で弟子たちを強め、「僕たちに、思い切って大胆に御言葉を語らせて下」さいます弟子たちの祈りに、地を揺らして応えて下さる生ける神様にすがり、私たちも励みたく願います。
◇2025年7月27日 使徒4:5-22 「イエスと共にいた者」
ペンテコステの日の出来事、弟子たちが数多くの国の言葉で神様の偉大な御業をたたえた後、物議が起こり、美しの門での癒しをきっかけにまた物議が起こりました。
役人、長老、律法学者たちはエルサレムに召集され、大祭司とその一族も集まりました。
万座のお歴々の前でペテロは何を語るのでしょうか。
「そのまん中に使徒たちを立たせて尋問した、『あなたがたは、いったい、なんの権威、また、だれの名によって、このことをしたのか』」
その厳かな場で、その真ん中に立たされ、緊張のあまり言葉を失いそうですが、何の権威、誰の名によってと聞かれれば、これはまさしくイエス様のお名前とその栄光とを証しするチャンスだったのです。
「その時、ペテロが聖霊に満たされて言った、…あなたがたご一同も、またイスラエルの人々全体も、知っていてもらいたい。この人が元気になってみんなの前に立っているのは、ひとえに、あなたがたが十字架につけて殺したのを、神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのである。」「人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、また同時に、ふたりが無学な、ただの人たちであることを知って、不思議に思った。そして彼らがイエスと共にいた者であることを認め、…」
民の指導者たちは学があっても何の権威も力もありませんでした。「イエスと共にいた者」であるかが大切なのです。
◇2025年7月20日 使徒3:21-4:4 「祝福にあずからせるため」
ヨエルの予言を引き、ダビデの預言を引き、ペンテコステの出来事を明確に説明したペテロは、神様はイエス様をメシア・救い主として立てられた方であり、聖書が預言している方であることを宣べ、人々は心を刺し貫かれ、多くの人たちが信じました。
それに続いて今日の箇所ではモーセや他の預言者たちの言葉や、神様がアブラハムに語られた言葉を通して聴く人たちにイエス様が確かに神様の元から遣わされ、聖書全体が証しするお方であることを語りました。
この、聖書全体からイエス様のことを証しする手法は、エマオの途上でイエス様が語られた方法と同じものでした。
「『ああ、愚かで心のにぶいため、預言者たちが説いたすべての事を信じられない者たちよ。キリストは必ず、これらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか』。 こう言って、モーセやすべての預言者からはじめて、聖書全体にわたり、ご自身についてしるしてある事どもを、説きあかされた。」
「あなたがたの兄弟の中から、ひとりの預言者をお立てになるであろう。その預言者があなたがたに語ることには、ことごとく聞きしたがいなさい」という御言葉、「地上の諸民族は、あなたの子孫によって祝福を受けるであろう」という旧約聖書の御言葉の本当の意味を、イエス様を焦点に見ることによって知ることが出来ます。イエス様を生活の焦点にする時、私たちも人生の意味を知るのです。
◇2025年7月13日 使徒3:11-20 「イエスの名が、それを信じる信仰のゆえに」
「彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっているとき」。
美しの門にて癒しを受けた男性の心は神様の御業の取り次ぎ手であるペテロとヨハネにくぎ付けになっていました。
人々の好奇の眼差しに対してペテロは言いました。
「イスラエルの人たちよ、なぜこの事を不思議に思うのか。また、わたしたちが自分の力や信心で、あの人を歩かせたかのように、なぜわたしたちを見つめているのか。」
私たちは美しの門にて、じっと男性を見つめて、「わたしにあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい」と言ったペテロの大胆さに驚くのではないでしょうか。そんなことを言ってもしも何も起こらなかったら恥をかくのではないかと…。しかしペテロは「自分の持っているもの」を明確に知っていました。それは自分の力や信心ではなく、自分の業ではなくて、「イエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、この人を強く」するのだという事でした。
「神はあらゆる預言者の口をとおして、キリストの受難を予告しておられたが、…このように成就なさったのである。…自分の罪をぬぐい去っていただくために、悔い改めて本心に立ちかえりなさい。」
イエス様の到来による救いは、長い昔から予告されていたことでした。それは私たちの罪がぬぐわれるため、そして私たちが心を入れ替えて向きを変えて出発できるためです。ここに素晴らしい知らせがあります。
◇2025年7月6日 使徒3:1-10 「わたしにあるものをあげよう」
主のお約束の通り、聖霊が注がれたペンテコステの日、聖霊によりペテロは力強い説教をしました。ヨエル書を引き、ダビデの言葉を引き、イエス様こそが「神は、主またキリストとしてお立てになった」方であることを証しし、人々の誤った考えと行いを明らかにしました。聞く人々は深く心を刺され、一日に三千人が主を信じて洗礼を受け、新たな仲間となりました。
「この曲った時代」。しかし教会には喜びと真心に満ちた愛し合い助け合う雰囲気が満ち溢れ、それが人々の好意を得、日々主は救われる人たちを仲間に加えて下さいました。
そんな中、「美しの門」で新たな奇跡が起こります。
生まれつき足の不自由な人が、日々援助者たちの手によってこの門のところに運ばれ、宮もうでにくる多くの人たちに施しを求めることで辛うじて生きる糧を得ていました。そんな中ペテロとヨハネがそこを通りかかりました。
彼らはこの美しの門に座る人に対して何を思って彼をじっと見つめたのでしょうか。そしてペテロらもまた「私たちを見なさい」と言いました。
「金銀はわたしには無い。しかし、わたしにあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい」金銀に勝る贈り物が与えられました。彼は大喜びで立ち上がり、飛び跳ねて喜び、神様をほめたたえて歩き回りました。彼の人生はイエス様の御名によって一変しました。主の御名には力があります。
◇2025年6月29日 使徒2:38-47 「日々心を一つにして」
ヨエルが預言した通り聖霊が人々に注がれ、それはイエス様が正しい方である証拠であり、そしてダビデがわが主と呼び、「彼は黄泉に捨ておかれることがなく、またその肉体が朽ち果てることもない」と神様によってあらかじめ語られていたのが他ならぬイエス様であり、「あなたがたが十字架につけたこのイエスを、神は、主またキリストとしてお立てになったのである」と力強く証ししたペテロでした。人々は強く心を刺され、「わたしたちは、どうしたらよいのでしょうか」と言いました。
恐ろしき的外れの罪の思いによる神様に対する高ぶりと、主であるイエス様を十字架につけた行いから私たちを救うものは何でしょうか。しかしその救いこそがイエス様の十字架でした。贖いの代価が支払われているので、私たちは悔い改めるだけで救われるのです。そして賜物としての聖霊さえ受けることが出来る。この良き知らせを聞いて、「曲がった時代から救われよ」との励ましと、力強い語り掛けに、三千人もの人たちが洗礼を受けて仲間になりました。彼らは教えにひたすら心を注ぎ、教えを守り、交わりをして聖餐を共にし、祈り過ごしました。心の奥底から畏れの心、神様を畏れかしこむ心が生まれ、その思いを持つ者同士も自然と心を一つにして持ち物を分け合い、一つ思いで親密な関係を持ち続けたのです。それゆえ彼らは好意を得て群れはますます広がっていきました。
◇2025年6月22日 使徒2:25-38 「わたしは常に目の前に主を見た」
イエス様は聖霊についてこう語られました。
「しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名によってつかわされる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、またわたしが話しておいたことを、ことごとく思い起させるであろう。」(ヨハネ14:26)
聖霊の働きにより、ペテロは堂々と説教をしました。聖霊が注がれた事を通してイエス様の語っておられたことが真実であったことを示し、聖霊が注がれることはヨエル書に書かれてある通りだと語りました。そのうえ、ダビデもまたイエス様のことをわが主と呼び、その復活をも預言していたとペテロは語ります。
詩編の中(16・110篇)でダビデが自らの苦しみとそこへの助けを歌っていたと思われることが、イエス様の身に起こる苦しみと、復活の預言であるという事を読み解く出来事には、聞く人たちを大変驚かせ、ダビデが主と呼んだそのお方をあなた方は十字架にかけて殺したのですという彼の言葉は、人々の心に深く刺さりました。聖霊の洞察力をもって私たちも聖書を読み、理解し、主が語られたことを思い起こし、今週も良き業に励みたいと願います。
「わたしを信じる者は、またわたしのしているわざをするであろう。そればかりか、もっと大きいわざをするであろう。…わたしはあなたがたを捨てて孤児とはしない。あなたがたのところに帰って来る。…あなたがたは心を騒がせるな、またおじけるな。」 (ヨハネ14章)
◇2025年6月15日 使徒2:14-24 「主の名を呼び求める者は、みな救われる」
使徒1章には弟子たちのこの悲痛な叫びがありました。
「主よ、イスラエルのために国を復興なさるのは、この時なのですか」
神の民イスラエルはローマの属州となり、エルサレムにはローマからの総督がいました。
国の独立を、復興を願う声があり、救い主(メシア)を待望する声がありました。
今日のペテロの説教には旧約聖書ヨエル書からの引用がありますが、ここにも敵国から攻められる神の民の悲惨が預言されています。
「酔える者よ、目をさまして泣け。…一つの国民がわたしの国に攻めのぼってきた。その勢いは強く、その数は計られず、その歯はししの歯のようで、雌じしのきばをもっている。」しかしヨエルは主にある守りをも預言します。
「地よ恐るな、喜び楽しめ、主は大いなる事を行われたからである。野のもろもろの獣よ、恐るな。…シオンの子らよ、あなたがたの神、主によって喜び楽しめ。…あなたがたはイスラエルのうちにわたしのいることを知り、主なるわたしがあなたがたの神であって、ほかにないことを知る。わが民は永遠にはずかしめられることがない。その後わたしはわが霊をすべての肉なる者に注ぐ。…すべて主の名を呼ぶ者は救われる。」
ペテロは、今神の民が置かれている状況を聖書から的確に引用し、そのために「主の名を呼ぶ」必要を説き呼ぶべき御名は、他ならぬイエス様の名であることを伝えたのです。
◇2025年6月8日 使徒2:1-13 「神の大きな働きを述べる」
今日はペンテコステ(聖霊降臨日)です。これは主の復活の日から50日目の日です。
イエス様は「聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろう」と語られましたが、果たしてこの日、聖霊により、弟子たちは世界中の人々の生まれ故郷の言葉で神の大きな働きを述べ、これを機に世界宣教が始まります。今からおよそ2000年前のこの日は教会の誕生日と呼ばれます。
「火のような、分かれた舌」が現れて弟子たちのうちに座を定めた時、弟子たちは聖霊に満たされ、「聖霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出し」ました。
「舌」という言葉は、言語という意味をも持ちます。聖霊は、まず彼らに新しい舌(言語)を与える働きをしました。そのことにより、弟子たちは習いもしない外国の言葉で語り始め、五旬祭(7週の祭り・刈り入れの祭り)のためにエルサレムに集まってきた人たちをも含め、多くの人たちの驚きとなりました。「これは、いったい、どういうわけなのだろう」、どんな方法で、どのようにして、このようなことが可能になるのだろうかというようなことが起こりました。神の聖霊がそれを可能にしました。神の聖霊が「神の大きな働きを述べ」させました。使徒行伝は「聖霊行伝」とも呼ばれます。神の大きな働きが弟子たちを動かすのです。
◇2025年6月1日 使徒1:3-11 「地のはてまで、わたしの証人となる」
先週はマタイ28章にあります主の大宣教命令を読みました。
「わたしは、天においても地においても、いっさいの権威を授けられた。それゆえに、あなたがたは行って、すべての国民を弟子とし…」とありました。
主が最高の権威者であり、力あるお方であるがゆえに、それゆえにそのお方の弟子と導くことに意味があります。
「時期や場合は、父がご自分の権威によって定めておられる…ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろう」
この箇所でも明確に、私たちは父なる神様の権威と力とによって聖霊をいただき、イエス・キリストの証しをする者であることが記されています。「権威」という言葉には権利、能力、超自然的な力、統治する力という意味があります。
聖霊が下るとき、私たちもまた権威者から授かった力を受け、この世の中を全て統治するお方からの力を受けてイエス・キリストの証し人とされるのです。そのための証印が聖霊です。そのための支えが、そのための後ろ盾が聖霊です。聖霊は私たちに下り、私たちのうちに入り、共に住み、私たちを神様の力に満たし、必ずや私たちを、地の果てまでもイエスキリストの証人としてくださるのです。「世の終りまで、いつもあなたがたと共にいる」と語られる主を頼みとして今週も進みましょう。
◇2025年5月25日 マタイ28:16-20 「いつもあなたがたと共にいる」
主があんなにもはっきりと死と復活の予告をしておられたのに、主の復活後に弟子たちは困惑し、信じられず、恐れ惑っていました。そんな弟子たちに主は何度も何度も現れ、ご自分が確かに復活なさったことをお示しになられ、御言葉を語り励まし、大漁の奇跡を再び見せて弟子たちの、いわば信仰の復活のためにお心を砕かれました。
幾度も幾度も現れてくださり、お姿を見せてくださり、限りないほどに弟子たちに触れる機会を作ってくださったのに、今日の箇所にありますように、その復活のイエス様を礼拝しながらも未だ疑う弟子もいたとのことにびっくりします。
何度も何度も現れ、御言葉を語り、奇跡の御業を見せて弟子たちを励ましてくださったのに、またすぐにその出来事を忘れ、目の前に主を見ながらも、主を拝しながらも主を疑う。主がそこにおられるのにもかかわらず主が分からない。弟子たちが繰り返し繰り返し道に迷うこの姿を、ペンテコステ前の出来事から何度も何度も読んでまいりました。
主はその都度その都度弟子たちが分かるまで共に歩き、語り続け、ご自身の姿をお見せになり、奇跡の業を行い、弟子たちが信じられるようにと忍耐強く接してくださいました。そして主は「世の終りまで、いつもあなたがたと共にいる」と語られ、弟子たちに使命を与えられました。共におられる主を信じ、御言葉に応答するのなら、奇跡を見ることが出来るのです。
◇2025年5月18日 ヨハネ21:1-19 「わたしに従ってきなさい」
感動的な奇跡の出来事と共に弟子たちへの主のご愛あふれる、牧歌的な湖畔の出来事が書き表されています。
まさにルカ5章のペテロらへのイエス様からの働きかけ、語り掛けの再来です。
あの時、イエス様は不漁に悩むペテロらに「沖へこぎ出し、網をおろして漁をしてみなさい」と言われ、ペテロは「先生、わたしたちは夜通し働きましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網をおろしてみましょう」と言いました。こうして主の言葉に聞き従った時、
「そしてそのとおりにしたところ、おびただしい魚の群れがはいって、網が破れそうになった。」と記してありました。ペテロは絶対起こりもしないことを引き起こす方を前に、疑った自分を恥じて「これを見てシモン・ペテロは、イエスのひざもとにひれ伏して言った、『主よ、わたしから離れてください。わたしは罪深い者です』」と語ると、主は「恐れることはない。今からあなたは人間をとる漁師になるのだ」と語られました。 「そこで彼らは舟を陸に引き上げ、いっさいを捨ててイエスに従った。」とありました。
今回も「一切を捨ててイエス様に従う」というレッスンが与えられました。もはや恐れることはない。力なく涙し、嘆くことも、失望することもない。イエス様は全てを統御しておられるお方なのです。この方に導かれる人は幸いです。私たちも主への導き手として用いられたいと願います。
◇2025年5月11日 ヨハネ20:19-31 「信じる者になりなさい」
今日も主の復活の日に起こった事を読んでまいりましょう。
「わたしたちは主にお目にかかった」と何度も何度もトマスに語る他の弟子たち。それはあなたもそこにいれば良かったのに、イエス様に会えたのにと言わんばかりです。
しかしトマスはトマスで、逃してしまったチャンスはどうにもならないが、イエス様に出会ったと言いながらほかの弟子たちはどうしてそんなに周りを恐れてびくびくしているのかという不満もあったことでしょう。
やはり集いには一人一人皆が必要であるという事が教えられます。互いに助け合い、補い合って一つの群れが出来上がっていると教えられるのです。誰かがいれば、誰かがいなくても大丈夫というわけではないのです。教会には、トマスの洞察力と、一度見たらもう迷わないという彼の一本気の性質が必要でした。そして教会には、どんなに危険が及んでも、望みが薄くなったように思っても、それでも主に期待し続けて礼拝に出席し続ける兄弟姉妹が必要です。
イエス様は彼らに3度「安かれ」と語られ、平安があるように、そして調和があるようにと語られました。そして「信じない者にならないで、信じる者になりなさい」と語られました。「信仰を持ち続けなさい」と語られました。見ずとも信じる。目に見える状況によらず、目に見えないが確かにおられ、救ってくださる方を信じる。神様に信仰を持ち続けたいと願います。
◇2025年5月4日 ルカ24:36-53 「聖書を悟らせるために心を開いて」
イエス様は「なぜおじ惑っているのか。どうして心に疑いを起すのか」と語られましたが、そういう疑いや惑いが弟子たちの間に、二千年前の復活の朝に充満していました。
そこでイエス様は、「聖書を悟らせるために彼らの心を開いて言われた」(45節)とあります。これは直訳しますと、「御言葉を理解するところの彼らの心、思い、動機、態度、意志、理解力と識別力を開いた」という事になります。私たちが心をかたくなにして殻に閉じこもり、信仰の心を閉ざすのは、実に御言葉を理解しようとする思い、理由、動機、意図、意志、態度の欠如、それらの心が閉ざす時に起こるのだ、つまり御言葉を理解しようとする熱意や思いや態度が薄れるときに私たちは横道に逸れてしまうのだということが分かります。
イエス様は「聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、またわたしが話しておいたことを、ことごとく思い起させるであろう」(ヨハネ14:26)と語られました。イエス様が語られたこと、すなわち御言葉を弟子たちが忘れたことが彼らの混乱の原因でした。
「見よ、わたしの父が約束されたものを、あなたがたに贈る」と主は言われましたが、御言葉を思い起こさせる、御言葉への情熱を燃やしてくださる方こそがまさしく、私たちの生き方を導く力となるのです。「もしわたしたちが御霊によって生きるのなら、また御霊によって進もうではないか」(ガラテヤ5:25)
◇2025年4月27日 ルカ24:13-35 「イエスご自身が彼らと一緒に歩いて行かれた」
先週は喜びあふれるイースター、主の復活をお喜びする日でした。しかし女性たちは生きている方を死者の中に探そうとしました、イエス様は確かに亡くなられて、その亡骸に香油を施そうと訪ねた女性たちからしたら無理からぬことですが、女性たちの、イエス様を死者の中に探す企ては失敗しました。そのことが無意味であることを天使たちははっきりと示し、主が語られた御言葉を思い出しなさいと言いました。
女性たちはそれと気付き、主の弟子たちのもとに戻り、事実をありのままに話しましたが、果たして弟子たちはそれを愚かな話、たわごと、ナンセンスで空虚な話と決めつけて信じませんでした。
私たちは見るべきものに目を留めず、思い出すべきものを思い出さず、信ずべきものを信じることが出来ず、ナンセンスと決めつけて信じずに、しかし途方に暮れ、説明も出来ず、困惑するのみです。しかしそんな不毛な議論に明け暮れる者たちに近づき、寄り添い歩き、御言葉を熱心に解き明かして信仰へ、希望へ、勝利へと導いてくださる主が共におられるという事を知るとき、私たちの心はまさしく燃えるのではないでしょうか。
「キリストは必ず、これらの苦難を受けて、その栄光に入る」。私たちはこの主イエス様を見失わないようにしたいと思います。ですから私たちもまた困難を恐れません。私たちが主の苦しみに会うとき、主の復活にもあやかれると信じるからです(ローマ6:5)。
◇2025年4月20日 ルカ24:1-12 「なぜ生きた方を死人の中にたずねているのか」
子羊の血を塗った家に死が過ぎ越す出来事を見ました。そして荒れ野を行く民に天からマナが降りました。
イエス様は最後の晩餐で、パンを取って「これは、あなたがたのために与えるわたしのからだである」と語られ、ぶどう酒を取って「この杯は、あなたがたのために流すわたしの血で立てられる新しい契約である」と語られました。
またイエス様はこうも語られました。「わたしは命のパンである。あなたがたの先祖は荒野でマナを食べたが、死んでしまった。しかし、天から下ってきたパンを食べる人は、決して死ぬことはない。わたしは天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者は、いつまでも生きるであろう。わたしが与えるパンは、世の命のために与えるわたしの肉である。…わたしの肉はまことの食物、わたしの血はまことの飲み物である。わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者はわたしにおり、わたしもまたその人におる。生ける父がわたしをつかわされ、また、わたしが父によって生きているように、わたしを食べる者もわたしによって生きるであろう。」
イエス様はそのお体をも血潮をも、ご自分の命を明け渡され、十字架に死なれましたが復活されました。
アンパンマンが自分の顔を人に食べさせて力無き者となりながらも、新しい顔を得て元気百倍に新たに立ち上がるように、イエス様は復活なさいました。私たちはそんなイエス様と共に生きているのです。
◇2025年4月13日 ルカ22:7-34 「わたしの血で立てられる新しい契約」
いよいよ受難週に入りました。今週の金曜日は受難日です。先週は出エジプトの出来事を読みました。主は「わたしは、エジプトにいるわたしの民の悩みを、つぶさに見、また追い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。わたしは彼らの苦しみを知っている」と語られました。
時は過ぎ、主イエス様の時代、過越の祭りの時期が来ました。今日もユダヤ人たちは過越の食事をしますが、苦菜と種入れぬパンと共に子羊の骨付きローストを食すのですが、この子羊の料理が犠牲の子羊を象徴するとのことで、民がエジプトを脱出した今日では、家の鴨居に血を塗ることまではしないようです。
イエス様は屠られる前の日の夜、最後の晩餐をしましたが、そこでパンとぶどう酒を弟子たちに与え、「これは、あなたがたのために与えるわたしのからだである。わたしを記念するため、このように行いなさい」、そして「この杯は、あなたがたのために流すわたしの血で立てられる新しい契約である」と語られました。
私たちの主イエス様はそのお体を私たちの罪のためのいけにえとしてささげ、その血潮をもって私たちを罪と死の呪いから救い出すために、罪と死からの出エジプトを果たすために新しい契約を、その血潮をもって与えてくださいました。その御身体と血潮の捧げものによって私たちはもはや鴨居の血を捧げる必要なく死からの過越を頂くのです。この血潮がなければ私たちを罪から救うものはないのです。
◇2025年4月6日 出エジプト記12:1-32 「これは主の過越の犠牲である」
シナイ山にてモーセに主なる神様は現れ、彼に使命をお与えになりました。「わたしは、エジプトにいるわたしの民の悩みを、つぶさに見、また追い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。わたしは彼らの苦しみを知っている。わたしは下って、彼らをエジプトびとの手から救い出し…」しかしモーセは初めにはためらい恐れて言いました。「ああ主よ、わたしは以前にも、またあなたが、しもべに語られてから後も、言葉の人ではありません。わたしは口も重く、舌も重いのです」そこで神様は言われました。
「だれが人に口を授けたのか。話せず、聞えず、また、見え、見えなくする者はだれか。主なるわたしではないか。それゆえ行きなさい。わたしはあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えるであろう」
そして彼はついにエジプトの王の前で「我が民を去らせよ」と語ります。
心をかたくなにするエジプトの王を前に神様は九つの災いを下されます。
それでも王がかたくなであるのを見て主は初子の死を定められます。人の罪はどこまでも深くて底知れぬものです。まことに「罪の支払う報酬は死」です。しかし主は「これは主の過越の犠牲である」という子羊を用意してくださいました。主は重々しい人の罪のため贖いを用意して、その裁きから「イスラエルの人々の家を過ぎ越して、われわれの家を救われた」のです。
◇2025年3月30日 出エジプト記1:1-2-10 「助産婦たちは神をおそれた」
あの幸いなヨセフ物語の結末を私たちは見届けました。しかしヤコブに神様から次のような言葉がありました。
「わたしはあなたと一緒にエジプトに下り、また必ずあなたを導き上るであろう」(創世記46:4)
こうしてエジプトに移住して約350年が経ち、ヨセフを知らない新しい王が即位しました。これはエジプトの体制が変化したことを指すのかもしれません。
ここからイスラエル人への敵視政策が始まりました。
「イスラエルの子孫は多くの子を生み、ますますふえ、はなはだ強くなって、国に満ちるようになった」この繰り返して描かれるイスラエルの繁栄は、神様が天の星のように、地のちりのように子孫を多くするとの約束の通りでした。
これを見てエジプト人はイスラエル人の上に重い労役を課しましたが、イスラエル人たちは苦しめられれば苦しめられるほどにいよいよ増え広がり、エジプト人たちはイスラエル人のゆえに恐れました。
そしてついにエジプトの王は助産師に命じて生まれてきたのが男の子ならば殺すように命じましたが、助産師たちは神を恐れるがゆえに命に従わず、彼女らは神様の恵みを受け、民は増え、非常に強くなりました。
後にモーセと名付けられる男の子も、愛と祈りの中、良きアイディアが生まれ、神様はそのすべてを守られ、いのちの道が開かれます。パロの娘の手を通して導かれたのは他ならぬ神様ご自身でした。
◇2025年3月23日 創世記44:12-45:28 「神は命を救うために私を遣わされた」
ヨセフの兄弟たちはエジプトの地で面倒に巻き込まれ、互いにこう語り合いました。「確かにわれわれは弟の事で罪がある。彼がしきりに願った時、その心の苦しみを見ながら、われわれは聞き入れなかった。それでこの苦しみに会うのだ」
あれから20年。人は蒔いたものを確かに刈り取らなければならないことが示されます。罪を隠しおおせたと思っても、絶対権力者の前に立たされ、罪科を償うときがやってきます。しかしヨセフは彼らにやさしく接しました。彼は雇人にこう言わしめました。
「安心しなさい。恐れてはいけません。その宝はあなたがたの神、あなたがたの父の神が…袋に入れてあなたがたに賜わったのです」(43:23)
そして彼は弟ベニヤミンをかばう兄ユダのこの言葉を聞きます。「どうか、しもべをこの子供の代りに、わが主の奴隷としてとどまらせ、この子供を兄弟たちと一緒に上り行かせてください」
この言葉に、彼らが真剣に父と弟のことを思う気持ちを察し、ヨセフはこう語ります。
「わたしはあなたがたの弟ヨセフです。あなたがたがエジプトに売った者です。しかしわたしをここに売ったのを嘆くことも、悔む(責め合う)こともいりません。神は命を救うために、あなたがたよりさきにわたしをつかわされたのです」彼らの中に不和の芽を見ながらも、彼の心には赦しと祝福がありました。残虐な行いをも救いに変える主の慈しみの御業を畏れます。
◇2025年3月16日 創世記42:1-38 「確かにわれわれは弟の事で罪がある」
ヨセフ物語を読み進めております。ついにヨセフと兄たちが再会する場面です。
「ヨセフの兄弟たちはきて、地にひれ伏し、彼を拝した」ヨセフの見た夢は20年以上の時を経て、果たしてその通りになりました。
私たちは神様のなさることの遠大さにただ驚くばかりです。伝道の書の3章です。
「天が下のすべての事には季節があり、すべてのわざには時がある。…神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお、人は神のなされるわざを初めから終りまで見きわめることはできない。」
ヨセフにとっては長い長い時の末に知らされた神様の御業の完結でした。同様に、神様はヨセフの兄たちの罪をそのままにはしておかれませんでした。
「彼らは互に言った、『確かにわれわれは弟の事で罪がある。彼がしきりに願った時、その心の苦しみを見ながら、われわれは聞き入れなかった。それでこの苦しみに会うのだ』」
私たちは全ての私たちの罪に対しての帰結を自分で刈り取らなければならないという恐れを抱きます。どうやって私たちは全ての罪の始末をすることが出来るでしょうか。ヨセフは王のように兄たちの前に君臨し、兄たちはひれ伏しています。報いを与える権威がヨセフにはありました。絶対的な権力者であられる天の父なる神様は私たちにどう報いられるのでしょうか。
◇2025年3月9日 創世記41:1-57 「神がわたしを悩みの地で豊かにせられた」
「神がわたしを悩みの地で豊かにせられた」。これは直訳すれば「神様は貧しくみじめな土地で私に真実であられた(実を私に結んでくださった)」となります。ついについにヨセフの苦労は報われました。この栄光のために彼はここに運ばれていたのだという神様の解き証し、種明かしが実現しました。
エジプトの王パロは、「聞くところによると、あなたは夢を聞いて、解き明かしができるそうだ」と言いましたが、
ヨセフは答えてこう言いました。「いいえ、わたしではありません。神がパロに平安をお告げになりましょう」。
神様は平安をお告げになられるお方です。神様は幸せと健康、人生の完成をもたらしてくださるお方です。私たちの願いに応え、応答し、そうしてくださるお方であることを証ししてくださいます。それは人がもたらすことが出来るものではありません。
「さとく、かつ賢い人」とは誰でしょうか。
「われわれは神の霊をもつこのような人を、ほかに見いだし得ようか」…パロがいみじくも言ったように、それは神の霊に頼るもの。神様を恐れ、仰ぎ、信頼し、従う者にこそふさわしいのです。
神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにして下さることを、わたしたちは知っている。(ローマ8:28)
◇2025年3月2日 創世記40:1-23 「解くことは神による」
「わたしは、実はヘブルびとの地からさらわれてきた者です。またここでもわたしは地下の獄屋に入れられるような事はしなかったのです」。
切実なヨセフの叫びです。兄弟たちの仕打ちにより穴に落とされ、奴隷商人に売り飛ばされ、ポテパルのもとで成功しかかったのもつかの間、えん罪でまたも地下の獄屋へ、低い低い穴倉にまたも転落させられるとは。どうしてかくも悲運が続くのか。もがくような苦労の末のせっかくの救いの糸口は、どうしてかくももろく自らのもとから取り去られていくのか。
穴へ穴へ、低きへ低きへ、絶望へと、数奇なる彼の人生はどうしてかくもうまくいかないのでしょうか。故郷の優しいお父さんの姿を思い出して彼は幾度牢の中で涙したことでしょうか。
しかし彼は王の囚人をつなぐ獄屋で、王の高官たちと話し、彼の将来の準備をここで、彼の屈辱の牢の中で得ることになります。その牢の中で、ヨセフは二人の人から夢の話を聞きます。そして彼は言いました。「解くことは神によるのではありませんか。どうぞ、わたしに話してください」
いみじくも彼が言った言葉、「解くことは神によるのではありませんか」という言葉の通りに彼の人生も導かれて行きます。私たちにはわからない謎が多いのですが、解き明かすのは私たち人間がするのではなく、神様のなさることです。神様は全てのことを相働かせ最善になさるお方です。
◇2025年2月23日 創世記39:1-23 「主がヨセフと共におられた」
父の溺愛を受け、他の兄弟たちの嫉妬を買うヨセフ。そしてついに親の目を離れたドタンの地で辛うじて殺される事だけは避けられましたが、ヨセフはエジプトへ奴隷として売られることとなりました。
「主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な者となり、その主人エジプトびとの家におった」。
様々な手の働きによって翻弄されるヨセフでしたが、神様は彼と共に、彼の近くに、ご一緒にいてくださいました。
その幸運と、主が彼と共におられ、彼の手のすることを主が栄えさせられるのを見て、ヨセフの主人は彼にすべてを任せ(与え)ました。
しかしポテパルの妻の虚偽により、主人は彼を牢に投げ入れ(与え)ます。
折角売られていった地で得た千載一遇のチャンスを、自分の落ち度でないことのゆえに失い、また暗闇に逆戻りするという事は、ヨセフにとってどんなに痛手だったでしょう。
しかしそれでも、その場にも主は彼の近くに、彼と共におられ、神様は看守長の好意を彼に与え、看守長は全ての囚人と、看守長の仕事とを彼に委ね(与え)ました。
神様はヨセフと共におられ、彼の手の業を祝し、導き、恵みと導きを絶えず与えてくださいました。
神様はヨセフと共におられ、彼を栄えさせられました。
神様は私たちのそば近くにおられ、私たちを祝し、私たちに良き働きを与え、手の業を祝し、栄えさせてくださることを信じましょう。
◇2025年2月16日 創世記37:1-30 「ヨセフを彼らの手から救いだして」
神様と顔と顔とを合わせて格闘し、神様ががっぷりと相対してヤコブの悩みと恐れとに向かってくださいました。「私を祝福してください」彼の強い願いは通じました。しかしそれは彼の勝利ではなくて、「神は勝利される(=イスラエル)」という出来事でした。兄のかかとをつかみ、長子の権利をかすめ取ろうとする彼の野心は打ち砕かれ、勝利者である神様の陰に隠れて祝福を願う信仰の人と作り替えられました。そして今一度ベテル(=神の家)にて彼は一家の偶像を捨て去り、「わたしの苦難の日にわたしにこたえ、かつわたしの行く道で共におられた神に祭壇を造ろう」と語り、主を礼拝しました。かつてはそこを未だ知れぬ所へ出ていく際の神様の守りを自分につなぎとめるための祭壇のような意味合いでしたが、今は違います。確かに守ってくださった神様への感謝と信頼と従順のしるしとなりました。
そして彼の12人の息子たちの物語が始まります。
今は亡き最愛の妻ラケルとの子ヨセフに上等な長衣を着せる父ヤコブのヨセフびいきに、他の兄弟たちは憎しみを増し加えていました。そんな中の彼の見た夢。兄弟たちは殺意を抱き、野を歩く彼を手にかけようとしますが、彼を守ろうとする長子ルベンと、後に家督を継ぐユダとによって辛うじて命は救われますが、奴隷として遠くに売られる身となりました。しかし巡り巡って民族をエジプトに導くことになろうとは、だれが想像できたでしょうか。
◇2025年2月9日 創世記32:9-32 「あなたを去らせません」
「わたしを祝福してくださらないなら、あなたを去らせません」。兄エサウのかかとをつかんで胎から出てきたヤコブらしい、神様への言葉です。
彼は人を押しのけ、兄エサウの長子の特権を自分のものとしました。そして彼は夢の中で天からのはしごを見たときに、神様に「わたしを守り、食べるパンと着る着物を賜い、
安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主をわたしの神といたしましょう」との言葉を語りました。それから彼は母リベカの兄ラバンに会います。ラケルをめとりたいと思いつつも姉からめとりなさいと言われ、計14年叔父に仕えるヤコブ。そして姉と妹の子作り競争が始まり、代理戦争にも似て二人の女性が加わり、今度はやがてその子たち同士の確執が生まれます。
ヤコブのゆえに神様はラバンの家を祝され、そのことを知るラバンは彼を手放そうとはしません。そんな中、あなたの先祖の国へ帰りなさいとの神様の言葉により歩を進めますが、その行く手には兄エサウがいます。
父イサクのたどった道のり、母リベカ、そしてエサウとヤコブ、叔父とその娘たち、様々の出来事が重なり、成功や祝福や神様の言葉による導きを得て、ヤコブのエサウとの再会の恐れの中、神様は彼の前に現れ、彼の全存在を身体で受け止めて彼の格闘の相手になってくださいました。神の家、神の顔。神様はどれだけ私たちと共におられ、受け止めて祝してくださるのでしょうか。
◇2025年2月2日 創世記28:10-22 「一つのはしごが地の上に立っていて」
先週の箇所からだいぶ飛びまして、ヤコブと主の梯子のお話となりました。アブラハムによって祭壇に捧げられたイサクでしたが、しっかり者のリベカと結婚します。子であるエサウとヤコブに恵まれますが、両親の思惑の違いも手伝って、長子の権利を与える時に大変な波乱が生じます。兄の殺意を知って逃亡する弟ヤコブ。その荒野の道中で、主は彼に語り掛けられます。
日本語には訳されていませんが、「見よ」との言葉が12節に2回、13節と15節に1回ずつあります。「見よ、はしごが据えられている。」
長子の権利をだまし取って命を狙われて逃亡の身となったヤコブですが、神様は彼のために天からのはしごを下ろされました。その事実を見よと聖書は語ります。はしごは据えられました。「はしごを外して孤立させる」ということわざがありますが、神様は失敗し、罪を犯し孤立している者にはしごを据えてくださいます。そして「見よ」、天からの使いがそのはしごを上がったり、下がったりしています。天使は初め低いところに、私たちと共にいて、まず上がり、そして神様の命を受けてまた降りてきます。ここにもイエス様のお姿を見ます。
「見よ」「わたしはあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。わたしは決してあなたを捨てず、あなたに語った事を行う」 私たちは見るべき事を知ります。ここは神の家です。
◇2025年1月26日 創世記22:1-14 「主の山に備えあり」
17章にて、わが子の誕生のお告げを頂き、どうして百歳の自分と九十歳の妻のもとに子が生まれようかと笑い、妻もまたその知らせに苦笑したのでした。しかし果たして神様のおっしゃったとおりにイサクが生まれました。神様は人知を超えた御業を昔も今もなさるお方です。
そしてその折角授かった愛息を全焼のいけにえとしてささげよとのお告げがあります。何という残酷なお告げでしょうか。ここに来て、喜んで育てたわが子を屠れとは、子孫を増やすために子を与えられたのに、その言葉は嘘だったのかと、耳を疑う神様の言葉でした。「神はアブラハムを試みて彼に言われた」。どうして神様は彼を試す必要があったのでしょうか。神様はご自分のみ告げを一笑に付した彼への意趣返しをしようとされたのでしょうか。
しかし彼はここで何の不服も表わさず、何の問いかけもせず、翌朝早く起きて黙々とその命令に実行しようとします。そしてそのいけにえの場所に着き、息子を縛って薪の上に置き、イサクも従います。
しかし神様はイサクに危害を加えることをお許しにはなりませんでした。
「あなたの子、あなたのひとり子をさえ、わたしのために惜しまないので、あなたが神を恐れる者であることをわたしは今知った」そしてイサクの代わりに一頭の雄羊。これはまさに私たちのために身代わりのいけにえであるイエス様をくださった神様の物語なのです。
◇2025年1月19日 創世記15:1-21 「わたしはあなたの盾である」 「あなたは…わたしが示す地に行きなさい。わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の基となるであろう。あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろう。地のすべてのやからは、あなたによって祝福される」との神様の言葉を受け、アブラムは75歳にして新たな出発をしました。その後飢饉を避けてエジプトに入り、妻サライをめぐっての出来事があったり、周辺の王たちによるロトの襲撃への奪還劇などがありました。 主は「アブラムよ恐れてはならない、わたしはあなたの盾である。あなたの受ける報いは、はなはだ大きいであろう」と語られましたが、彼にはその報いを受け継ぐべき子がいませんでした。 主なる神様は言いました。「天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみなさい…あなたの子孫はあのようになるでしょう」ルカ福音書のザカリアを思い出します。 「アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。」信仰による義というテーマは、もうここに現れています。「主なる神よ、わたしがこれを継ぐのをどうして知ることができますか」アブラムは主を信じたと聖書は語りますが、それでもアブラムはしるしを求めました。神様は600年以上も後の出エジプトのことまで語られ、彼の子孫のための贖いによる救いを示されます。まことに、「主はわが盾」です。
◇2025年1月12日 創世記12:1-8 「わたしが示す地に行きなさい」 新たな年となりまして、1月も、はや半分が過ぎました。 大変に寒い日々が続いております。お元気にお過ごしでしたか。 先週は年初とのことで創世記1章から御言葉を味わい、今日は創世記12章、アブラムが75歳にして神様の示す地に出発した出来事を読み進めてまいりましょう。 思えば、アブラムの父テラは、アブラムとその妻サライ、そして孫であるロトを連れて、ウルからハランまで、1000km以上もの距離を移動し、そこで亡くなりました。 神様はアブラムに、さらに800キロメートル離れたカナンへの移動を命じられます。父との別れの地を去り、もうこれ以上は移動したくないという親族もいたのかもしれません。神様は「国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、わたしが示す地に行きなさい」と語られました。 心細い小さな集まり。しかし神様はこう約束なさいました。 「わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の基となるであろう。」 神様は小さな民を偉大にし、祝福し、全世界への祝福の基となさいます。私達日本のクリスチャン、そしてこの教会の私たちは小さい群れかもしれませんが、神様が偉大にして祝福のもといとするとの御言葉を噛み締めましょう。私たちはいつも礼拝の場に戻り、祈りと心を捧げて主を待ち望みます。
◇2025年1月5日 創世記1:1-5 「神はその光とやみとを分けられた」 新年のご挨拶を申し上げます。 年の初めに天地創造の聖書の箇所を味わいましょう。 「はじめに神は天と地とを創造された」。ここには何も神の起源については記してありません。神様は永遠の昔からおられ、これからも永遠に生き続けるお方、世界の創造の起源であるお方です。ここには「天と地」、「闇と光」、「昼と夜」、「夕と朝」という対極が列記されています。 「地は形なく、むなしく、やみが淵のおもてにあり…」ここには、原初世界の空虚と混沌、無為と寂しさとが満ち、従ってそれはすなわち闇であったと記してあります。そして、底知れぬ水、底が見えない深淵、地獄のようなどん底の表面に不気味に暗闇が覆っているのです。何という恐ろしい原初世界なのでしょう。そこは光明も命もない世界なのです。 そして、従って、それから、神の霊(息)はその深淵の水の上をホバリングするのです。舞い駆けて巡るのです。親鳥が巣の卵やひなを気にかけて、寵愛して羽で新鮮な風を送って温度を調整して生きる環境を整えるように、聖霊が駆け巡っていました。 ついに神様は「光あれ」と言われ、光が出来ました。そして、従って、神様は光と闇とを分けられたのです。闇は光から隔絶されました。深淵の混沌も、茫洋とした世界も、空虚さもむなしさも、光の後に隔絶されました。ここに光として、人の命として来られたイエス様の贖いを見ます。